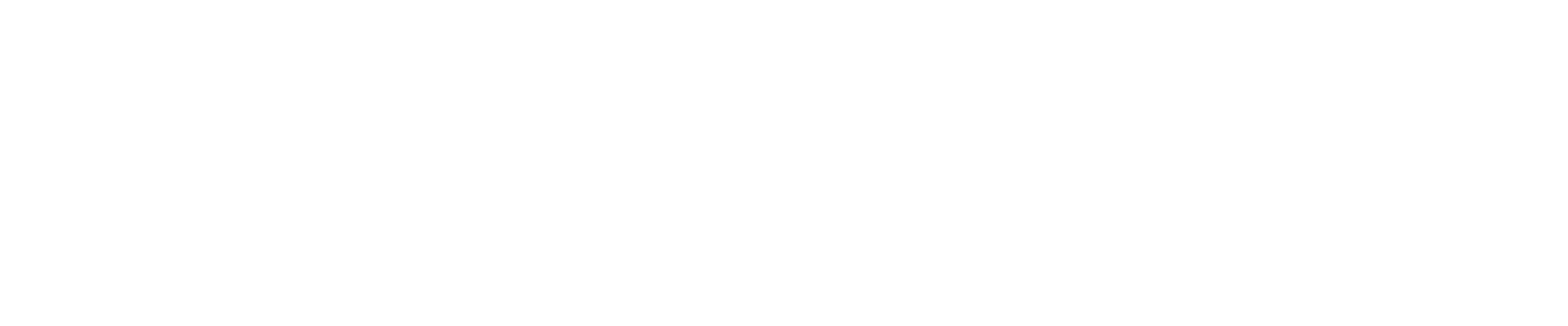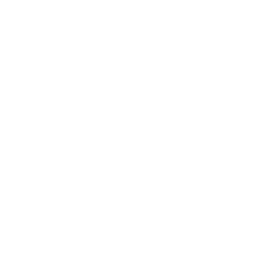- エーコー様について
- 防盗金庫・耐火金庫などの各種セキュリティ製品の製造、販売
- エーコー様
- お話をお伺いした方
- 営業本部 首都圏営業部 課長 兼 業務担当課長 S.D 様
経営支援システム課 課長 S.Y 様
- お客様の課題
- データ管理が属人化しており、情報が各所に散在している
- 他部門の情報が見えていない
- マスタ管理のルールが整っていない
- 課題解決の成果
- 情報の一元管理とリアルタイム共有
- 部門間連携の強化
- マスタ整備が進み情報を資産として活用
- ご利用モジュール
- UM工程進捗UM販売購買
※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた内容に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述している場合がございます。
株式会社エーコー(以下、エーコー)様は、セキュリティ製品の製造・販売を中心に行う総合メーカーです。特に金庫や耐火製品の分野で高い専門性をお持ちです。防犯・防災・情報保護の観点から、法人・官公庁向けに高品質なセキュリティ製品を提供されており、特に金庫の分野では国内トップクラスの実績を誇る企業です。






今回、UM SaaS Cloud導入のプロジェクト責任者であるS.D 様と、プロジェクトリーダーであるS.Y 様にインタビューさせていただきました。
コロナ禍をきっかけとした、営業DXと製販一体システム構築への挑戦
システム導入を検討し始めたきっかけは何ですか?
(S.Y 様)従来、当社(エーコー)では、訪問を中心とした営業スタイルを展開してまいりましたが、コロナ禍以降、対面での営業活動が制限され、売上にも影響が生じました。このような環境変化を受け、営業活動のデジタル化は急務と判断し、まずは顧客管理・営業支援の基盤として、各社員の営業活動を数値で測るためSalesforceを導入することにしました。
さらに、Salesforce導入を契機に、これまで営業部門と製造部門でバラバラに管理されていた情報を一元化する体制の構築を目指し、基幹システムの刷新にも着手しました。この刷新を通じて、製販一体のシステムで部門間の連携を強化したいと考えました。
情報がバラバラで仕事が進まない!部門間の壁と非効率な情報共有の課題
UM SaaS Cloudの導入前はどのような課題を感じていましたか?
(S.Y 様)当社では、長らく営業部門と製造部門がそれぞれ独自に商品マスタを管理しており、情報の分断が課題となっていました。
各部門間で業務内容や運用ルールの共有が十分に行われておらず、互いの作業実態を把握できないまま、推測や憶測に基づいた対応が常態化していました。データの統合作業は、担当者が不在のため「やる人がやる」という属人的な管理方法になり、データの整合性が取れていませんでした。結果として、必要な情報共有は電話やビジネスチャット(Slack)で担当者に直接連絡しないとわからない、という状態が続いていました。
このような状況は、業務効率の低下やコミュニケーションの齟齬を招くだけでなく、商品情報の整合性や迅速な意思決定にも支障をきたしていました。



営業・製造連携を実現!Salesforceと柔軟な製品管理
UM SaaS Cloudを選んだ決め手を教えてください。
(S.Y 様)Salesforceとの連携が可能であり、営業部門で管理している顧客情報や受注データと、製造部門の生産管理情報をシームレスに統合できる点が大きな選定理由となりました。これにより、部門間の情報共有が促進され、受注から製造までの業務プロセスを一貫して管理することが可能となりました。
また、当社が取り扱う製品は、金庫をはじめとした箱物製品全般にわたり、仕様変更や個別対応が多く発生する点が特徴です。UM SaaS Cloudは、こうした多品種・変動型の製品構成に柔軟に対応できる設計となっており、現場の実態に即した運用が可能です。
これらの点から、Salesforceとの親和性と製品特性への適合性を両立できる本システムは、当社の業務改善と情報統合を実現する最適なソリューションであると判断いたしました。
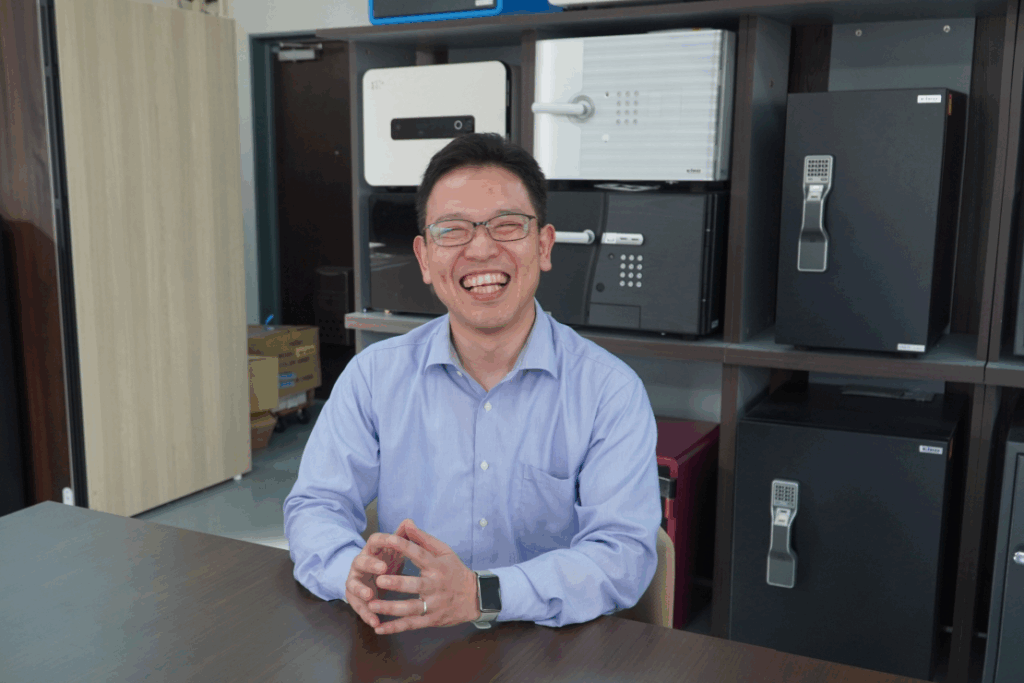
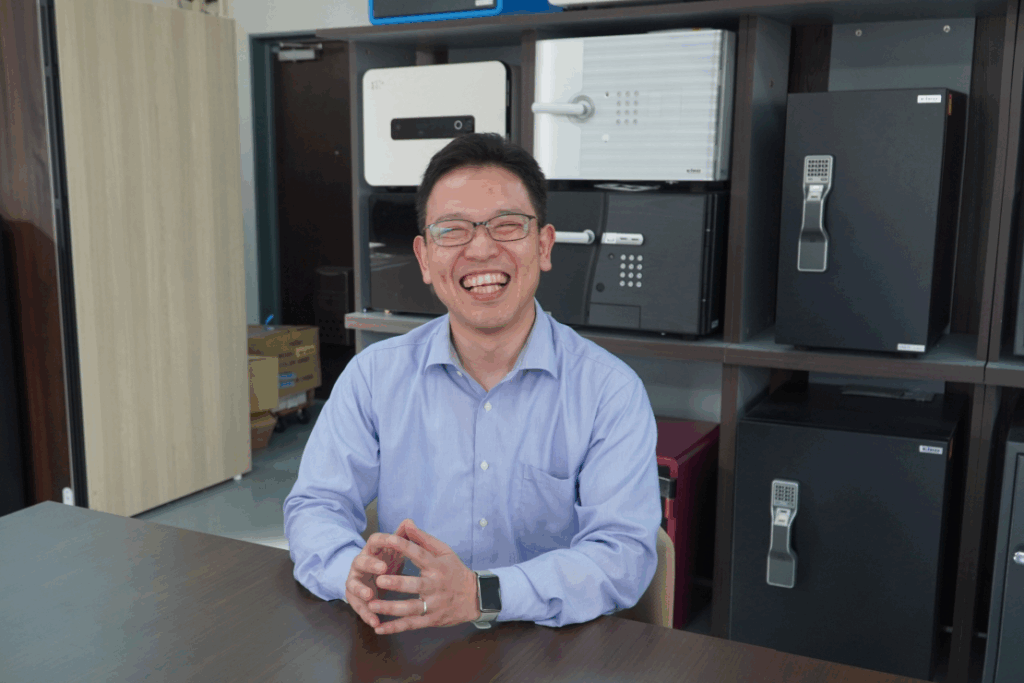
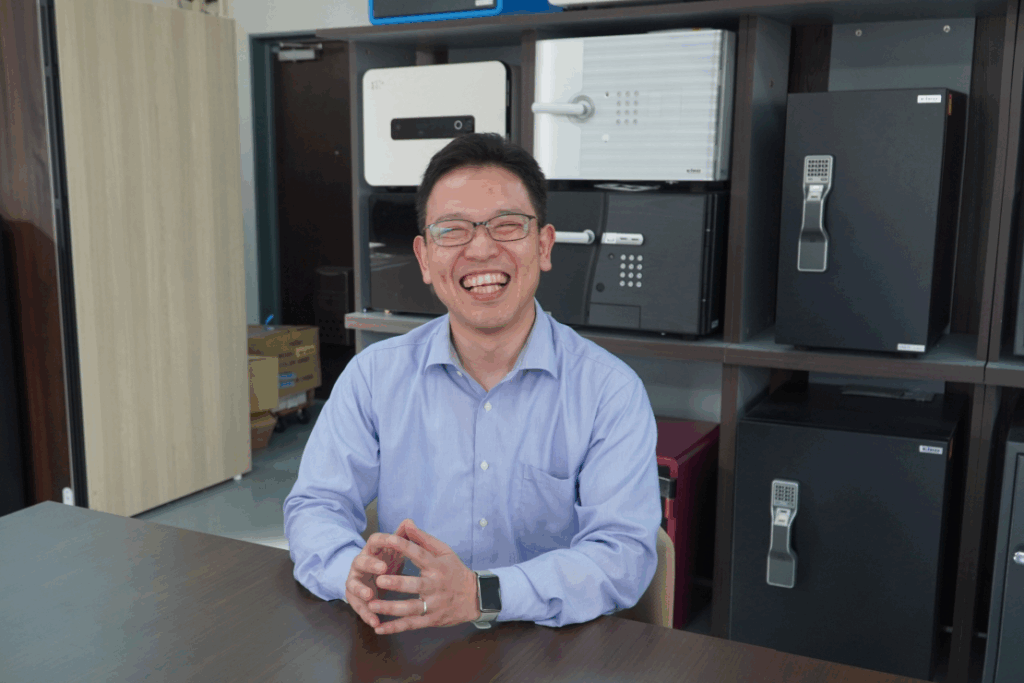
システム活用を加速!社員が主役となって進める帳票づくり
UM SaaS Cloudをどのように利用していましたか?
(S.Y 様)現在は、UM販売購買が本稼働、UM工程進捗を導入中という段階です。
UM販売購買では販売管理として、受注データや売上データ、在庫データなどを管理しています。また、必要な帳票については、自社で帳票開発ツールを活用し開発しています。
自ら手を挙げて帳票作成に取り組んでくれた社員の行動がきっかけとなり、社内で作成する動きが生まれました。帳票作成は今後導入するUM工程進捗でも必要なので、仕事内容を理解している社内で作成できるというのは、とてもいいですね。
「人に頼る」から「データで動く」組織への転換
導入後、どのような変化がありましたか?



(S.Y 様)これまで当社のマスタデータ管理は属人的かつ断片的で、情報の正確性や共有性が大きな課題でした。
結果として業務の属人化や更新漏れも発生しやすく、部門間の連携を妨げていました。
そこで、システムの導入・連携を進めたことで、情報の一元管理とリアルタイム共有が可能となり、業務の透明性とスピードが大きく向上しました。部門間のコミュニケーションも円滑化され、現場からのフィードバックや進捗確認が即時に行える体制が整いつつあります。
さらに、これまで曖昧だったシステム運用に対して、専任のシステム管理部門を新設したことで、データ品質の維持や運用ルールの整備が進み、社内全体として「マスタデータを資産として扱う意識」が定着し始めています。
これらの取り組みにより、業務の属人化を解消し、情報精度・業務効率・顧客対応力の向上といった複数の面で着実な改善が見られており、今後のさらなる業務標準化とDX推進に向けた基盤が整いつつあります。特に、レポートやダッシュボードを活用し、ヒューマンエラーを未然に防ぐための運用を整えることができました。
販売から生産までの全工程を見える化し、さらなる業務連携の強化へ
今後、UM SaaS Cloudを使ってやっていきたいこと、期待していることはありますか?
(S.Y 様)UM工程進捗の導入によりマスタデータの統一と生産状況の可視化を進め、UM販売管理と合わせて活用することで、部門間の連携強化を図っていきたいと考えています。